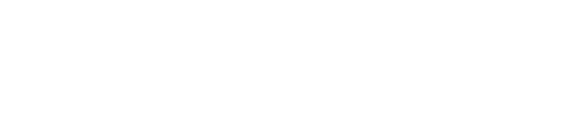COLUMN
コラム
S006|法人設立日の決め方|法人市民税(均等割)の初年度計算と名古屋市の例、許認可・社会保険の留意点
法人を設立する際に最初に直面するのが「設立日をいつにするか」という問題です。
設立日は会社にとっての「出生日」にあたり、一度決めると変更することはできません。
もっとも、設立日そのものは税務計算上、大きな影響を及ぼすものではありません。名古屋市の法人市民税(均等割)においても、月割計算により数千円程度の差が生じる場合はありますが、決算日の選定に比べれば影響は限定的です。
それでも、実務上は設立日を決めるにあたり、いくつか考慮すべき観点があります。以下に代表的なポイントを整理します。
縁起を担いだ日を選ぶケース
多くの方は、大安や一粒万倍日などの吉日に合わせたり、ご自身やご家族の誕生日に合わせるなど、記念日として意味を持たせることを重視されます。
税務や許認可の観点から大きな差がない場合には、記念性を重視するのも一つの考え方です。
月初を避けることによる税務上の効果
税務上の観点では、均等割の月割計算に注意が必要です。
均等割は法人住民税(法人市民税・法人県民税)の最低課税額で、名古屋市の法人市民税の公式ホームページでは次のように説明されています。
均等割額が月割となる場合は、均等割額(年額)に事務所等が所在していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算します。この場合の月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数は切り捨てます。ただし、事務所等が所在していた期間が1か月未満の場合は、1か月とします。
たとえば「1月2日設立・12月決算」の場合、初年度は11か月分の負担で済みます。
一方で「1月1日設立」であれば12か月分となり、たった1日の違いで約7,000円の差が生じることになります。
注意点
- 均等割の金額は資本金や従業員数によって異なります。一般的に資本金1,000万円以下の法人では7万円が目安ですが、規模が大きいと増額されます。
- 月割計算による軽減効果は初年度のみであり、2期目以降は事業年度が12か月になるため影響はありません。
- 本コラムでは名古屋市を例に挙げていますが、法人県民税や他の市町村(岡崎市など)の法人市民税でも同じ仕組みが適用されます。
事業開始日や許認可から逆算するケース
実務的には、事業開始日や許認可取得日から逆算して設立日を決めることも多いです。
- 宿泊業や建設業など、許可が必要な業種 → 許可が下りる日を基準に設立日を設定
- 取引先との契約や融資実行に合わせたい場合 → 契約開始日や入金予定日に設立日を合わせる
なお、具体的な許認可の要否や申請日程については、必ず所轄の官公庁に確認するか、行政書士などの専門家にご相談ください。当事務所にて事前に打ち合わせを行っている方には、必要に応じて専門家をご紹介することも可能です。
脱サラ・社会保険の注意点
特に「脱サラ」による独立で法人を設立される方は、社会保険の切替に注意が必要です。
たとえば月末に退職 → 翌月中旬に法人設立といったケースでは、一度国民健康保険に切り替えた後、協会けんぽへ再度切替を行う必要が生じることがあります。
余計な手続きを避けるためには、設立日や退職日の調整を事前に検討することが望ましいでしょう。労務関連については社会保険労務士にご相談ください。
設立日が決まったら
設立日を定めた後には、実際の手続きが待っています。
- 法人設立登記の手続き → 司法書士に依頼するケースが一般的です。
- 許認可が必要な業種の申請 → 行政書士に相談するのが安心です。
- 法人設立後の税務署・県市町村への届出 →当事務所がサポートします。
- 社会保険・労務関連の手続き → 社会保険労務士の専門分野です。
どの専門家に何を依頼すべきか、判断に迷う方も少なくありません。
当事務所と顧問契約をいただいているお客様には、必要に応じて司法書士・行政書士・社会保険労務士などの専門家をご紹介しています。特別な費用負担はなくご利用いただけますので、安心してご相談ください。
まとめ
- 設立日は「会社の出生日」であり、一度決めたら変更できない。
- 名古屋市の法人市民税(均等割)は月割計算で、月初を避けることで初年度のみわずかに軽減可能。
- 均等割額は資本金・従業員数により異なり、制度自体は法人県民税や他市町村でも同じ仕組み。
- 縁起や記念日を重視するケースも多い。
- 事業開始日・許認可取得日から逆算する実務的な判断も必要。
- 脱サラ時には健康保険の切替に注意。
- 設立後の登記・許認可・税務・労務は専門家に相談を。必要に応じて当事務所から紹介も可能。
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [コラムまとめページはこちら]