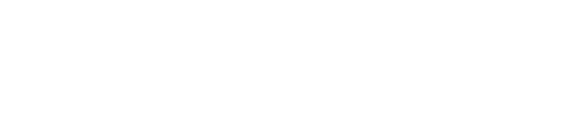COLUMN
コラム
社長の経費が招く「トリプルパンチ」の恐怖と、責任ある線引き
「誰でもできる簡単節税!」──インターネットや書籍で、こんな甘い言葉を目にする機会が増えました。しかし税理士として日々現場に向き合う私から見れば、その中には「節税」という言葉を拡大解釈し、極めて危険な領域に踏み込んでいる情報が散見されます。
当事務所は、こうしたセンシティブなテーマについて積極的な発信を控えてきました。なぜなら「節税」を売り文句に、法の趣旨を逸脱するような提案をする一部のコンサルタントや無資格者と一線を画したいと考えているからです。
しかし、誤った情報に振り回され、会社や経営者が大きなリスクを背負う事態を防ぎたい。そこで今回あえて、税理士としての責任ある見解をお伝えすることにしました。
節税と脱税──越えてはならない一線
まず整理すべきは「節税」と「脱税」の違いです。
- 節税:税法に認められた制度を活用し、正当に税負担を軽減する行為(例:iDeCo、ふるさと納税、税額控除など)。
- 脱税:事実を偽り、不正に納税を免れる行為(例:売上除外、架空経費)。
両者の間には「合法か違法か」という決定的な違いがあります。
特に多くの誤解が見られるのは、「社長のプライベートな支出(家事費)を会社の経費にする」という行為です。これは節税ではなく、れっきとした脱税です。
法律上も明確に否認される「家事費」
ここで重要なのは、家事費や私的支出を経費にできないことは、単なる解釈論ではなく、法律に明確に定められている点です。
- 所得税法第45条
「納税者の家事上の経費およびこれに関連する経費は、必要経費に算入しない」と明記されています。 - 法人税法第34条
「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない」と規定されています。
→ ここでいう損金とは、税務上「会社の利益計算において経費として認められる金額」のことを指します。会計帳簿上は費用として処理できても、税務計算上は損金として認められない場合があるのです。つまり、交際費や旅費交通費など別の科目で処理しても、実態が役員のプライベート支出=給与であれば損金にはならないのです。 - 国税庁タックスアンサー No.5202「役員に対する経済的利益」
法人が役員に資産を無償または低額で提供したり、債務を免除したり、個人的費用を会社が負担するようなケースは、すべて「役員に対する経済的利益」として給与と同様に扱われます。
このように、役員個人の支出は条文レベルで否認されるものであり、「節税テクニック」などではなく、明確に脱税にあたります。
トリプルパンチが会社を直撃する
法人が役員の私的支出を負担した場合、税務上は「役員賞与」と認定されます。そこから始まるのが、いわゆる「トリプルパンチ」です。
- 法人税の追徴
役員賞与と認定されると損金に算入できず、利益が加算され法人税が増加。 - 源泉所得税の追徴
本来天引きすべき源泉所得税を会社が納めていないため、源泉徴収義務違反とされます。
会社は追徴課税や加算税を課されるほか、当然役員本人から源泉所得税を徴収しなければならず、双方に大きな負担が残ります。 - 消費税の追徴
給与と認定されるため仕入税額控除は認められず、消費税の追加納付が必要に。
この「トリプルパンチ」の悲惨さを理解すれば、安易に家事費を経費にすべきでない理由は明白です。
「攻めの節税」と家事費経費化は別物
最近は「攻めの節税」という言葉もよく耳にします。
しかし、どんなに攻めの姿勢を強調しても──「家事費を経費にする」ことだけは決して許されません。
YouTube広告や一部のコンサルタントは「ディズニーランドのチケットも経費にできる」と大げさに宣伝します。
確かに、ディズニーの魅力を紹介するユーチューバーが実際に園内で撮影するのであれば、合理的関連性があります。
しかし、社長が家族と遊びに行くチケットを「経費」とするのはまったくの別物です。
「保守的な税理士は厳しすぎる」と批判されることもあります。
ですがその厳しさこそ、調査に耐えうるラインであり、会社を守る安全弁です。派手な節税話に乗って経費化に挑戦するのは、あくまで自己責任であり、税理士として推奨できるものではありません。
経費かどうかを見極める思考フレーム
経費計上の判断に迷った際、私はお客様に次の2点を自問いただくようお伝えしています。
- その支出は「事業のため“のみ”」ですか?
- 税務調査官に胸を張って説明できますか?
少しでも「プライベートも兼ねている」「後ろめたさがある」と感じるなら、それは経費ではありません。
最後に──責任ある節税を
私はひとり税理士として、一件一件に責任を持って向き合います。
決して耳障りの良い節税スキームを推奨することはありません。むしろ、リスクを最小限に抑え、安心して経営に専念いただけるようサポートすることが使命だと考えています。
「これは経費になるのか?」と迷ったときは、ぜひ壁打ち相手としてご相談ください。責任ある判断を共に考えることが、税理士の役割です。
【ご注意】
本コラムは当事務所の見解であり、日本税理士会連合会その他団体を代表するものではありません。本内容に基づく行為について当事務所は責任を負いかねます。具体的判断は必ず顧問税理士へご相談ください。