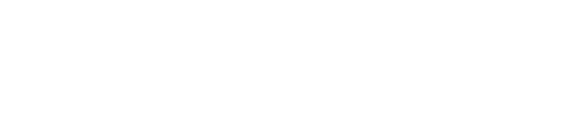COLUMN
コラム
S005|法人設立時の決算月はいつ?税理士が解説する“後悔しない選び方”と2割特例への影響
岡崎・名古屋エリアを中心にスタートアップや中小企業をサポートしている税理士の安藤です。
設立前から1期目まで、これまで10件ほどの法人設立をお手伝いしてきました。
法人設立時に必ず聞かれるのが、
「会社の決算月(決算日)はいつに設定すればよいか?」
というご相談です。
決算月は自由に選べますが、安易に決めてしまうと「資金繰りが苦しくなった」「想定以上に税金が増えた」と後悔することもあります。
ここでは、法人設立時に押さえておきたい 決算月の選び方と4つの戦略 を税理士の立場から解説します。
戦略1:会社自身の繁忙期を避ける 〜棚卸・売掛金・買掛金〜
会社にとっての「繁忙期」は本業の忙しさだけでなく、決算作業の負担が一気に増える時期でもあります。
棚卸の負担
決算では、その時点で残っている商品・材料・製品を数えて評価します。
- 仕入れた商品が残っていれば「在庫」として資産計上
- 製造途中のものは「仕掛品」として翌期に繰り越し
つまり、材料費や外注費を払っていても売上につながっていなければ経費にはならず、結果的に利益が膨らむことになります。
期末に在庫や仕掛品が多いと棚卸作業そのものが膨大になり、決算処理全体が圧迫されます。
※ 棚卸とは?
商品・材料・製品を一つひとつ数え、期末にどれだけ残っているかを把握する作業のこと。
「資産」と「経費」を分けるために必須で、小売業や製造業では特に大きな負担になります。
売掛金・買掛金の管理
決算期には「売掛金」や「買掛金」も多くなりがちです。
- 売掛金:商品やサービスを販売したが、まだ代金を受け取っていない債権
例:3月に納品、入金は4月 → 3月末は「売掛金」として計上 - 買掛金:仕入や外注費を受けたが、まだ代金を払っていない負債
例:3月に外注納品、支払いは4月 → 3月末は「買掛金」として計上
決算期に売掛金・買掛金が多いと、未収入金や未払金の突合・証憑整理が増え、仕訳数が膨らんで自己管理も煩雑になります。
また、売掛金や買掛金は「勘定科目内訳明細書」に一つずつ記載して税務署に提出する必要があり、件数が多いほど事務負担が大きくなるのです。
戦略2:売上のピークに合わせて資金繰りを安定させる
経営において最も重要なのは資金繰りです。
おすすめは、売上のピークから2〜3か月後に決算月を設定することです。
売上入金が多い時期に納税資金を準備できるため、余裕を持って決算・申告を迎えられます。
逆に売上が落ち込む時期に決算を設定すると、納税資金が足りず資金繰りが苦しくなるリスクがあります。
また、売上ピーク直後は一般的に繁忙期も落ち着き、支出も比較的安定してくる時期です。
そのため、決算月は「資金が潤沢で、かつ慌てずに準備できる時期」を選ぶのが理想です。
戦略3:消費税「2割特例」を最大限に活かす
2023年10月に始まったインボイス制度では、免税事業者の負担を軽減するため「2割特例」が設けられています。
この特例は 2026年9月30日を含む事業年度まで に限定されており、設立時の決算月の設定によって効果が変わります。
具体例:2025年11月設立(1期目からインボイス適用)の場合
- 10月決算にした場合
- 第1期(2025/11/1〜2026/10/31) は2026年9月30日を含むため、2割特例の対象。
- 第2期(2026/11/1〜2027/10/31)は2026年9月30日を含まないため特例対象外。簡易課税or本則課税を選択することになる。
- 8月決算にした場合(1期目を短縮)
- 第1期(2025/11/1〜2026/8/31) も2026年9月30日以前に属するため特例の対象。
- 第2期(2026/9/1〜2027/8/31) も2026年9月30日を含むため特例の対象。
この場合、第1期と第2期の両方で特例を利用でき、2期目も特例を当てられる点が有利。
注意点
- 免税事業者(インボイス未登録) の場合は申告義務がなく、2割特例を意識する必要はありません。
- 課税事業者のみ決算月設定によって有利不利が変わります。
- インボイスの判断にはその他の条件(売上規模・取引先の要請・業種特性など)も関わります。必ず税務署や顧問税理士に確認してください。
詳細は 国税庁ホームページ をご参照ください。
戦略4:税理士の繁忙期を避けてコミュニケーションを確保する
法人の決算は自由に設定できますが、12月〜3月決算は特に注意が必要です。
- 12月決算 → 2月申告
個人の確定申告と時期が重なり、税理士事務所は最繁忙期を迎えます。 - 3月決算 → 5月申告
昔ながらの法人の多くが3月決算を選んでおり申告が集中。さらに ゴールデンウィークで稼働日数が限られるため、税理士の負担が増えます。
このような繁忙期に決算が重なると、
- 相談へのレスポンスが遅れる
- 打ち合わせが短縮され、十分な助言が得られない
- 追加料金が発生する場合もある
といった影響が出やすくなります。
逆に、繁忙期を避けた決算月にすれば、税理士と腰を据えてコミュニケーションをとり、経営判断や資金繰りの相談をじっくり行えるというメリットがあります。
まとめ:法人設立時は「戦略的に決算月を選ぶ」ことが大切
法人の決算日は一度決めると変更が難しく、最初の判断がその後の資金繰りや節税に直結します。
特に以下の4つの戦略を押さえると、初年度から後悔しにくい決算月を選べます。
- 戦略1:会社自身の繁忙期を避ける 〜棚卸・売掛金・買掛金〜
- 戦略2:売上のピークに合わせて資金繰りを安定させる
- 戦略3:消費税「2割特例」を最大限に活かす
- 戦略4:税理士の繁忙期を避けてコミュニケーションを確保する
愛知県(岡崎市・名古屋市など)で法人設立をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
スタートアップや中小企業の状況に応じて、最適な決算月をご提案いたします。
また、会社設立にあたっては 司法書士や社会保険労務士と提携し、登記や労務手続きも含めてトータルでサポート しております。
愛知県(岡崎市・名古屋市など)で法人設立をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
スタートアップや中小企業の状況に応じて、最適な決算月をご提案いたします。
また、会社設立にあたっては 司法書士や社会保険労務士と提携し、登記や労務手続きも含めてトータルでサポート しております。
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [コラムまとめページはこちら]