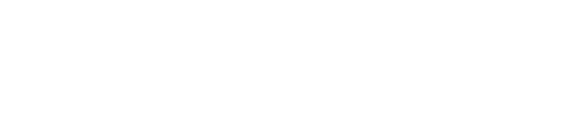COLUMN
コラム
A009|レシート・領収書の正しい保管方法|税理士が解説するクラウド会計を活用した管理法
「領収書やレシートをノートに貼って管理する」――昔ながらの経理スタイルを続けていませんか?
かつてはそれが当たり前でしたが、クラウド会計ソフトやOCR(文字認識)技術が普及した今、貼り付け管理はかえって非効率です。
本記事では、30代の若い税理士が実務経験をふまえて考える「これからの領収書・レシートの整理術」をご紹介します。
私はこれまで、愛知県内の複数の税理士事務所で勤務経験を積みました。
- 刈谷の事務所にいた頃は、領収書をノートに貼り付け、請求書は別管理というスタイルがまだ一般的でした。
- 名古屋市中区の税理士事務所では、逆に明確なルールがなく、担当者ごとに管理方法がバラバラで効率が悪いと感じたこともあります。
そうした現場経験と、現在クラウド会計ソフト(マネーフォワード・freee 等)を活用して記帳代行サービスや自計化指導を行っている立場から、当事務所としておすすめできる領収書・レシート管理法を解説していきます。
ノート貼付はOCRの妨げになる
マネーフォワードやfreeeといったクラウド会計ソフトは、スマホでレシートを撮影するだけで日付や金額を自動読み取るOCR機能を備えています。
しかし、ノートに糊で貼ってしまうと――
- 光の反射や糊跡で読み取り不良が起こる
- 端が切れて文字が欠ける
といった問題でOCRの精度が大きく下がります。
つまり、「ノート貼付」はOCR活用においてNGなのです。
👉 どうしてもノートに貼りたい場合は、OCR撮影を済ませた後に貼るようにしてください。
撮影後であれば、読み取り精度に影響を与えず、見た目の整理や紙ベースでの確認もしやすくなります。
OCRの精度はまだ60~70点。それでも使うべき理由
もちろん、現時点のOCRは完璧ではありません。
- 金額の誤読
- 店舗名や取引内容の欠落
- 入力項目の不足
などがあり、精度としては「60点~70点」レベルです。
しかし、ノート貼付や手入力に比べれば格段に速く、効率的。特に自計化している企業にとっては作業時間を大幅に短縮できます。
最強の整理術は「支払い手段 × 月ごと」
紙の証憑を残す場合は、支払い手段ごとに分け、さらに月ごとにまとめるのがベストです。
例:
- 現金払い(4月分/5月分…)
- 銀行引落(4月分/5月分…)
- 法人カード払い(4月分/5月分…)
この方法なら、後から「4月の法人カード払いの領収書を確認したい」と思ったときにすぐ取り出せます。
従来のように段ボールや封筒にまとめて突っ込むだけでは、どこに何があるかわからなくなり、しかも容量を大きく取ってしまいます。
シンプルに「支払い手段 × 月ごと」に整理すれば、検索性も保存効率も格段に向上します。
封筒より「2穴ファイル+リフィル」がベター
さらに実務的には、封筒よりも2穴ファイルにリフィルを入れて管理する方式がおすすめです。
Amazon等でも販売されている「A4ワイド対応リフィル」を使えば、領収書やレシートを支払ごと・月ごとに区切ってファイル化できます。
👉 参考リンク:A4ワイド 2穴リフィル(Amazon)
この方法には次のメリットがあります。
- 机の上でそのまま確認できる
- OCR撮影もしやすい(糊跡や反射なし)
- 月末・決算時にまとめて提出できる
- 請求書や納品書など他の経理書類も一緒に綴じられる
- 紙で税理士に提出する際も、そのまま送付できる
特に、リファイルに綴じたまま郵送すれば、領収書や請求書がバラける心配がありません。
心配な場合は、ファスナー付きバインダーを使うとより安全です。
👉 参考リンク:ファスナー付きホルダーリーフ(Amazon)
支払い方法は法人カードに統一するのが効率的
また、事業用の決済方法が多すぎると、ファイル分けの作業も複雑になります。
したがって、基本は法人カード払いに統一し、やむを得ない場合のみ現金払いにするのがベストです。
以前のコラム(経理が整う口座とカードの選び方【経営管理編1】)でも解説しましたが、決済方法を集約すれば仕訳もシンプルになり、クラウド会計との相性も向上します。
電子帳簿保存法と整理方法の注意点
「スマホで撮ったから原本は捨ててよい」という誤解がよくあります。
しかし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存方式」には、解像度や入力期限、改ざん防止措置など厳格な要件があります。
単純なスマホ撮影では法的に有効な保存と認められないため、むやみに廃棄するのは危険です。
実際には、領収書やレシートはファイル保管してもそれほど容量を取りません。迷ったら「まず残す」が安心です。
なお、電子帳簿保存法によりスキャン保存が認められ、一定の要件を満たせば原本を破棄できるケースもあります。
ただし、これはあくまで明確なルールに則って行う必要があり、要件を満たさなければ税務上認められません。
当事務所では基本的に紙の保管を推奨しています。
そして、領収書の整理方法については会計事務所によって異なるため、必ず顧問税理士に確認してください。
特に整理ルールが明確にされていない税理士事務所においては、本記事をぜひ参考にしていただければと思います。
まとめ|クラウド会計とOCRで効率化を実現
- ノート貼付はOCR精度を下げるのでNG
- どうしても貼るなら撮影後に貼る
- OCRは完璧でなくても効率性は抜群
- 段ボールや封筒での保管は非効率
- 保管は「支払手段 × 月ごと」が基本
- 封筒より「2穴ファイル+リフィル」で整理が便利
- 紙提出もリファイルならそのまま送付できる(ファスナー付きなら安心)
- 支払い方法は法人カードに統一するのが最適
- 電子帳簿保存法の要件を満たせば破棄も可能だが、当事務所は基本的に保管推奨
- 領収書の整理方法は会計事務所ごとに異なるため、顧問税理士に確認を
クラウド会計とOCRを活かした領収書・レシートの整理術は、経理時間を削減し、本業に集中できる環境をつくります。
「ノート貼付が当たり前」だった時代から変化した今こそ、正しい整理法を取り入れ、効率と法令遵守を両立させていきましょう。
弊事務所のサポートについて
私は岡崎市のひとり税理士として、最初から最後まで代表である私が直接対応いたします。
弊事務所では、
- クラウド会計を活用した記帳代行(経理を任せたい方向け)
- 自計化指導(ご自身で入力し効率化を図りたい方向け)
の両方を提供しています。
また、Googleドライブなどのクラウドストレージを使った資料のやり取りを基本としており、郵送や持参の手間を大幅に削減。
遠方のお客様でもスムーズにご依頼いただける体制を整えているため、全国対応が可能です。
「自計化を進めたいけれど不安がある」「領収書整理だけ任せたい」といった方も、それぞれの状況に応じて柔軟にサポートいたします。
クラウド記帳代行・自計化指導にご関心がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [コラムまとめページはこちら]