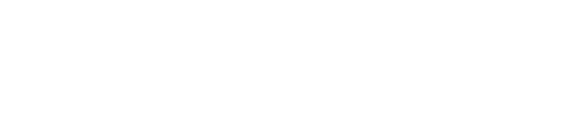COLUMN
コラム
A006|預り金の基礎知識|源泉所得税を正しく処理するための経理ルール
はじめに:こんなお悩みありませんか?
「税理士やデザイナーへの報酬から、なぜか税金が天引きされている…」
「源泉所得税の納付書が届いたけど、どうして支払う必要があるの?」
「7月10日までに上半期分の源泉所得税を納付するよう税理士から連絡がきた」
法人や、従業員に給与を支払っている個人事業主の皆様にとって、「源泉徴収」は避けては通れない業務です。しかし、その仕組みは複雑で、疑問に感じる点も多いのではないでしょうか。
特に、毎年7月10日は、「納期の特例」を受けている事業者にとって、1月から6月までに預かった源泉所得税を納付する重要な期限です。
本コラムでは、経営者の皆様が抱える源泉所得税のギモンを解消し、安心して事業に専念できるよう、その仕組みから納期の特例まで、専門家である税理士がわかりやすく解説します。
そもそも「源泉所得税(源泉徴収)」とは?
「なぜ、報酬を支払う側がわざわざ税金を預かって納めなければいけないの?」これは最もな疑問です。
通常、所得税は、個人が1年間の所得と税額を計算し、確定申告によって自ら国に納めるのが原則です。
しかし、特定の所得については、効率的に税金を徴収するため、報酬を支払う側(=事業者である皆様)が、支払いの際に所得税を天引きし、ご本人に代わって国に納めることが法律で義務付けられています。この仕組みを「源泉徴収制度」といい、天引きした所得税を「源泉所得税」と呼びます。
皆様の手元に届く納付書の「報酬・料金等」の欄は、この源泉徴収によって預かった税金を納めるためのものなのです。
どんな支払いが源泉徴収の対象になるの?
源泉徴収の対象となる報酬・料金は多岐にわたりますが、事業で関わることの多い代表的なものは以下の通りです。
- 税理士、弁護士、司法書士など、特定の資格を持つ個人への報酬
- 原稿料、講演料、デザイン料
- プロスポーツ選手、芸能人、モデル、外交員などへの報酬
- ホステス、コンパニオンなどに支払う料金
これらの報酬を支払う際は、源泉徴収が必要かどうか、一度立ち止まって確認する習慣をつけましょう。
【事務負担を軽減】源泉所得税の「納期の特例」とは?
源泉所得税は、原則として、徴収した月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、毎月の納付は事務手続きが煩雑です。
そこで、給与の支給人員が常時10人未満の事業者に限り、事務負担を軽減するための「納期の特例」という制度が設けられています。
この特例の適用を受けると、納付を年2回にまとめることができます。
- 1月~6月分 → 7月10日までに納付
- 7月~12月分 → 翌年1月20日までに納付
納期の特例を利用するには?
この特例を受けるには、事前に所轄の税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。申請書を提出した月の翌々月の納付分から、この特例が適用されます。
メリットと注意点
- メリット: 毎月の納付手続きがなくなり、事務負担が大幅に軽減されます。
- 注意点: 半年分をまとめて納付するため、1回あたりの納税額が大きくなります。資金繰りに影響が出ないよう、計画的に準備しておくことが重要です。また、納付忘れが起こりやすいため、カレンダーに登録するなど、期限管理を徹底しましょう。納期が遅れると、延滞税などのペナルティが発生します。
「前の先生は源泉徴収されなかったのに…」その理由は支払先が「法人」か「個人」か
「以前の個人税理士には源泉徴収していなかったのに、なぜ今の先生は必要なの?」という疑問もよく伺います。
その答えは、報酬の支払先が「個人」か「法人」かの違いにあります。
源泉徴収義務は、原則として個人の専門家に報酬を支払う場合に生じます。一方、税理士法人や弁護士法人といった「法人」へ報酬を支払う場合は、源泉徴収の必要はありません。
法人への支払いは、その法人の「売上」となり、法人が自ら法人税として申告・納税するためです。
【具体例】10万円の報酬を支払う場合(消費税は考慮しない)
ケース1:個人のA税理士に支払う場合
報酬額: 100,000円
源泉所得税(10.21%※): 10,210円
A税理士への支払額: 89,790円
事業者が国へ納付する額: 10,210円
事業者の総支出: 100,000円
ケース2:B税理士法人に支払う場合
報酬額: 100,000円
源泉所得税: 0円(不要)
B税理士法人への支払額: 100,000円
事業者の国へ納付する額: 0円
事業者の総支出: 100,000円
ご覧の通り、事業者の皆様が最終的に負担する総額はどちらのケースでも10万円で同じです。支払先が個人か法人かで、「お金の流れ(支払いルート)」が変わるだけなのです。
※復興特別所得税を含んだ税率です。
源泉徴収に関するよくあるギモン
Q1. 源泉徴収される専門家は「得」をしているの?
A1. いいえ、全く得をしていません。
源泉徴収された税金は、専門家にとって所得税の「前払い」に過ぎません。専門家は、確定申告の際に年間の所得税額を計算し、そこから前払いした源泉徴収税額を差し引いて、最終的な納税額(または還付額)を確定させます。つまり、この制度によって専門家が得をすることは一切ありません。
Q2. 従業員のいない個人事業主も、報酬の源泉徴収は必要?
A2. 原則として、必要ありません。
給与の支払いがない個人事業主の方は、そもそも「源泉徴収義務者」に該当しないため、税理士報酬やデザイン料などを支払う際に源泉徴収を行う義務は、原則としてありません。
まとめ:源泉徴収を正しく理解し、期限内の納付を
源泉徴収制度は、事業者にとって手間のかかる業務かもしれません。しかし、これは法律で定められた義務であり、円滑な税務行政のために重要な役割を果たしています。
- 源泉徴収は、支払者が特定の報酬から所得税を天引きし、本人に代わって国に納める制度です。
- 支払先が「個人」か「法人」かで、源泉徴収の要否が異なります。
- 「納期の特例」を利用すれば、事務負担を軽減できますが、事前の届出と計画的な納税資金の準備が必要です。
- 源泉徴収は専門家にとって税金の前払いであり、決して得をする制度ではありません。
7月の納期限が迫っている事業者様も多いかと存じます。この機会に源泉徴収への理解を深め、適切な納税手続きを心がけましょう。もしご不明な点があれば、お気軽に顧問税理士などの専門家にご相談ください。
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [コラムまとめページはこちら]