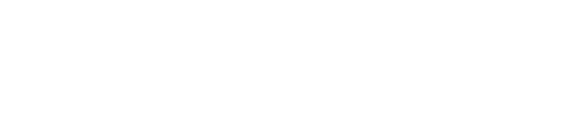【税理士が警鐘】その法人成り、後悔しますよ?税金と社会保険で失敗しない5つの注意点
「知り合いの社長が『法人成りして後悔している』と話していた…」
先日、お付き合いのある金融機関の担当者様から、こんなご相談を受けました。詳しく聞くと、法人化して節税になるはずが、逆に手元に残るキャッシュが減ってしまった、というのです。
なぜ、こんなことが起こるのでしょうか?
今回のコラムでは、安易な法人成りで後悔しないために、絶対に知っておくべき5つの注意点を、税理士の視点から解説します。
(本記事は、個人事業主と資本金1,000万円以下の中小法人を比較し、令和7年3月20日現在の税制に基づいています。)
法人成りで後悔する最大の理由とは?
結論から言うと、後悔する最大の理由は
「社会保険料」の負担増を甘く見積もっているからです。
法人化すると、たとえ社長一人でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が法律で義務付けられます。この負担額が、個人事業主時代の国民健康保険+国民年金よりも、はるかに高くなるケースが多いのです。
「税金は安くなっても、社会保険料がそれ以上に増えて、手取りが減った…」これが失敗の典型的なパターンです。
【注意点1】避けられない「社会保険料の壁」
個人事業主の国民健康保険料は前年の所得に応じて決まりますが、上限があります。一方、法人の社会保険料は役員報酬に比例し、上限額もかなり高額です。
|
個人事業主 |
法人 |
| 加入保険 |
国民健康保険 + 国民年金 |
健康保険 + 厚生年金 |
| 加入義務 |
任意(家族を扶養に入れる) |
社長一人でも強制加入 |
| 保険料負担 |
全額自己負担 |
会社と個人で折半(ただし総額は高くなる傾向) |
役員報酬を高く設定すると、社会保険料だけで年間100万円以上の負担になることも珍しくありません。
【例外】ただし、こんな場合は安くなることも
- 扶養する家族が多い場合
国民健康保険は加入者一人ひとりに保険料がかかりますが、社会保険は扶養家族が何人いても被保険者本人の保険料は変わりません。そのため、扶養する家族が多い方は、法人化によって世帯全体の保険料負担が軽減される可能性があります。
- 役員報酬を低く設定した場合
役員報酬を低く抑えれば、社会保険料は安くなります。ただし、将来受け取る年金額が減るなどのデメリットも伴うため、総合的な判断が必要です。
【補足】ご自身の国民健康保険料の確認について
国民健康保険料の計算方法は市区町村によって大きく異なります。ご自身の正確な保険料については、必ずお住まいの市区町村役場にご確認ください。
【注意点2】「経費にできる範囲」の誤解
「法人は経費にできる範囲が広い」と聞きますが、メリットばかりではありません。
| 項目 |
個人事業主 |
法人 |
| 自分への給与 |
経費にできない |
役員報酬として経費にできる(※) |
| 生命保険料 |
経費にできない(所得控除のみ) |
一定のルール内で経費にできる |
| 出張日当 |
経費にできない |
ルールを整備すれば経費にできる |
| 退職金 |
経費にできない |
経費にできる |
(※)役員報酬を経費にすると、社長個人には
給与所得控除という税制上のメリットが生まれます。しかし、このメリット以上に社会保険料の負担が重くなる可能性があるため、慎重な設定が必要です。
【注意点3】「赤字でも発生する税金」の存在
個人事業主は、赤字(所得ゼロ)なら所得税や住民税はかかりません。
しかし、法人は
たとえ赤字でも、法人住民税の「均等割」として最低でも年間約7万円を納税する義務があります。
【注意点4】税金だけの比較は危険!「手取り額」で考えよう
では、実際いくらくらいの利益から法人成りを検討すべきでしょうか。よく「利益800万円が目安」と言われますが、税金だけで比較するのは危険です。
ここで、
年間の事業利益が800万円の場合の、個人事業主と法人(社長の役員報酬800万円)の
「年間手取り額」をシミュレーションしてみましょう。
| 項目 |
個人事業主 |
法人(社長) |
| ①利益 / 役員報酬 |
8,000,000円 |
8,000,000円 |
| ②所得税・住民税など |
約 1,600,000円 |
約 870,000円 |
| ③国民健康保険・国民年金 |
約 1,040,000円 |
– |
| ④社会保険料(会社・個人合計) |
– |
約 2,280,000円 |
| 手取り(①-②-③) |
約 5,360,000円 |
– |
| 手取り(①-②-④個人負担分) |
– |
約 5,990,000円 |
※上記のシミュレーションは、特定の条件下での簡易的な概算値です。扶養家族の有無、各種控除の適用状況、お住まいの自治体など、個別の状況によって実際の金額は大きく変動します。あくまで両者の違いをイメージしていただくための参考値であり、その正確性を保証するものではありません。
このケースでは、税金は法人が圧倒的に安いですが、社会保険料の負担が重くのしかかります。会社負担分も考慮した
事業全体で残るキャッシュを比較することが重要です。
【注意点5】節税商品は「出口戦略」が必須
経営セーフティ共済(倒産防止共済)や生命保険など、掛金を損金(会社の経費)にできる節税商品は有効ですが、これらは
「課税の繰り延べ」、つまり税金の支払いを将来に先送りしているに過ぎません。
解約時には全額が利益として計上され、税金がかかります。そのため、役員の退職金支払いに合わせるなど、あらかじめ「出口戦略」を計画しておくことが不可欠です。
結論:法人成りはシミュレーションがすべて
法人成りは、正しいタイミングと計画で行えば、節税や信用力向上など大きなメリットをもたらす強力な戦略です。しかし、目先の税額だけで判断すると、必ず後悔します。
失敗しない唯一の方法は、
あなたの状況に合わせて「税金」と「社会保険料」の両方を考慮した、精密なシミュレーションを行うことです。
「自分の場合はどうなる?」「最適な役員報酬はいくら?」
あなたの状況をヒアリングし、精密なシミュレーションの必要性や今後の進め方についてアドバイスいたします。後悔のない選択をするために、まずはお気軽にご相談ください。
(※シミュレーションなどの具体的な金額計算は有料対応となります。)
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [
コラムまとめページはこちら]