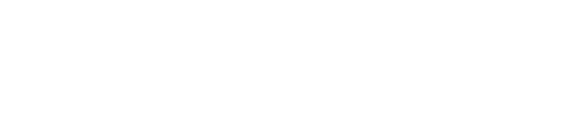COLUMN
コラム
2025.03.12
コラム
S001|創業時に迷うポイント|個人事業主として開業するか法人を設立するか
【税理士が徹底比較】個人事業主と法人設立、どっちが得?メリット・デメリットから選び方まで解説
「自分のアイデアで事業を始めたい!」 そう決意したとき、多くの人が最初に直面するのが「個人事業主としてはじめるか、法人を設立するか」という問題です。 自由な働き方、収入アップ、キャリア形成など、創業の目的は人それぞれ。しかし、事業形態の選択は、将来の税金、信用力、事業の成長性に大きく影響します。 そこで今回は、創業を考えるあなたのために、「個人事業主」と「法人(株式会社)」のどちらが適しているのか、メリット・デメリットを徹底比較し、専門家の視点から「あなたに合う」選択肢を解説します。一目でわかる!個人事業主と法人(株式会社)の違い
まずは、両者の違いを一覧表で見てみましょう。| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社) |
|---|---|---|
| 設立・開業の手間 | 簡単 (税務署に開業届を提出するだけ) | 複雑 (定款作成、登記、社会保険・税務手続きなどが必要) |
| 設立コスト | ほぼ0円 | 約25万円~ (定款認証や登録免許税など) |
| 社会的信用度 | 法人に比べて低い傾向 | 高い (取引や採用、融資で有利) |
| 責任の範囲 | 無限責任 (事業の負債は全財産で負う) | 有限責任 (原則、出資額の範囲で責任を負う) |
| 資金調達 | 融資のみ | 融資に加えて「出資」も可能 |
| 会計・税務申告 | 比較的シンプル | 複雑で、税理士への依頼が一般的 |
| 税率 | 所得税(5~45%) ※累進課税 | 法人税(約15~23.2%) ※所得に応じて変動 |
| 節税の選択肢 | 限定的 | 役員報酬や退職金など、選択肢が豊富 |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金に強制加入 |
| 赤字の場合の税金 | 所得がなければ所得税・住民税はかからない | 赤字でも法人住民税(均等割)が最低約7万円発生 |
| 事業承継 | 手続きが煩雑になりがち | 株式の相続でスムーズに行える |
| 廃業の手間 | 簡単 (廃業届を提出するだけ) | 複雑 (清算手続きに時間と費用がかかる) |
【税理士が解説】あなたはどっち?3つの判断基準
表を見ても「じゃあ、自分はどっち?」と悩んでしまいますよね。 ここでは、あなたがどちらを選ぶべきか、3つの判断基準をご紹介します。判断基準1:売上・利益の見込み
一つの目安は「年間の利益(所得)が800万円を超えるか」です。 個人の所得税は利益が上がるほど税率も高くなる「累進課税」です。利益が800万円~900万円を超えると、個人の税率が法人税率を上回る「タックス・クロス」が起こり、法人の方が税負担上有利になるケースが多くなります。- スモールスタートしたい、利益がそこまで見込めない → 個人事業主
- 初年度から高い利益が見込める → 法人
判断基準2:取引先や事業内容
誰と、どのようなビジネスをするかも重要なポイントです。- 一般消費者向け(BtoC)の事業、許認可が不要 → 個人事業主
- 大企業や官公庁と取引したい(BtoB)、建設業など許認可で法人が必須 → 法人
判断基準3:将来のビジョン
事業をどこまで大きくしたいですか?- まずは副業から、自分のペースで働きたい → 個人事業主
- 積極的に資金調達して事業を拡大したい、従業員を雇いたい → 法人
まとめ:あなたに合ったスタイルで、最適なスタートを
個人事業主と法人のどちらが良い・悪いということはありません。あなたの事業計画や将来のビジョンに合わせて、最適な形態を選ぶことが成功への第一歩です。- 個人事業主がお勧めな方: まずは手軽にスモールスタートしたい方。初期費用や維持費を抑えたい方。
- 法人設立がお勧めな方: 社会的信用を重視し、将来的に事業を大きく成長させたい方。節税も視野に入れたい方。
「自分の場合はどっちだろう?」「具体的な設立手続きが知りたい」 事業のスタート地点で悩んだら、専門家に相談するのが一番の近道です。当事務所では、あなたの状況に合わせた最適な事業形態のご提案を、初回30分無料で行っております。 提携する司法書士のご紹介も可能ですので、壁打ち相手としてお気軽にご相談ください。