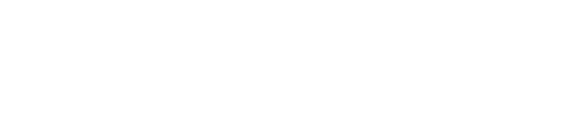COLUMN
コラム
A007|預り金が合わない3つの原因|税理士が解説する仕訳ミスと管理のポイント
会計ソフトの「預り金」が合わない!源泉所得税額とのズレ、3つの原因と正しい管理法を税理士が解説
「会計ソフトの『預り金』残高と、納付する源泉所得税の額が微妙に合わない…」
「給与計算は合っているはずなのに、なぜか預り金にズレが生じる…」
クラウド会計ソフトの普及でご自身で経理業務を行う方が増える中、このようなお悩みを抱えて不安に感じたことはないでしょうか?
この記事では、会社の経理で特に重要な「源泉所得税の納付」について、会計ソフト上の「預り金」残高がズレてしまう主な原因と、ご自身でできる確認のポイントを、税理士が分かりやすく解説します。
そもそも、なぜ「預り金」と「源泉所得税納付額」は一致するのか?
給与や報酬を支払う際、会社は所得税を天引き(源泉徴収)し、それを一時的に「預かり」、後日まとめて国に納付します。この「一時的に預かっているお金」を管理するのが、会計上の「預り金」という勘定科目です。
freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトは、給与計算や支払い処理を行うと、源泉所得税額を自動で「預り金」として計上してくれるように設計されています。
そのため、原則として、会計ソフトの「預り金」残高は、あなたが納付すべき源泉所得税の金額と一致するのです。
【原因別】預り金が合わない・ズレる3つのケース
原則は一致するはずなのに、なぜズレが生じてしまうのでしょうか?原因は主に以下の3つのパターンに分けられます。
Case 1:入力ミスや計上漏れ
最もシンプルですが、意外と多いのがこのケースです。
- 金額の入力ミス: 給与計算や仕訳を手入力している場合に金額を間違えた。
- 計上漏れ・二重計上: 過去の納付処理を忘れていたり、誤って二重に計上したりしている。
まずは入力内容に単純な誤りがないか、過去の仕訳と給与明細、納付書などを照らし合わせてみましょう。
Case 2:給与の「締め日」と「支払日」のタイミングのズレ
これは、ズレの原因として非常に多いケースです。特に「月末締め・翌月10日払い」のような場合に起こります。
源泉所得税を徴収する(預り金が発生する)タイミングは、法律で「給与や報酬を支払った時」と定められています。
これを「月末締め・翌月10日払い」の例で見てみましょう。
- 1月分の給与(1/1~1/31勤務分)
- 支払日: 2月10日
- 源泉所得税の徴収日(預り金が発生する日): 2月10日
- 国への納付期限: 3月10日
この流れで、2月末時点の「預り金」残高を確認するとどうなるでしょうか?
2月10日に徴収した1月分の源泉所得税が「預り金」として残っている状態です。これはまだ納付期限(3月10日)が来ていないため、1ヶ月分の源泉所得税が残高として表示されるのが正常な状態です。
【注意点】
会計ソフトの設定によっては、給与計算ソフトから連携した仕訳が、支払日(2/10)ではなく締め日(1/31)付で計上されることがあります。この場合、1月末時点の会計データ上には預り金が存在するのに、実際の納付は3月10日となり、一時的にズレているように見えます。これは会計処理上のタイミングの問題であり、最終的に解消されるズレです。
Case 3:年末調整による「預り金」のマイナス
年末調整の結果、従業員に還付する税額(返しすぎた所得税)が、その後に徴収する源泉所得税額を上回ることがあります。
- 例:12月分の給与で預かる源泉所得税が3万円なのに、年間の調整で還付すべき金額が5万円だった。
この場合、会社は2万円を「持ち出し」で還付することになります。会計ソフト上では、この状態が「預り金のマイナス残高」として表示されます。
これは「預かっているお金」以上に「還付すべきお金」が多い状態を示しており、年末調整後の正しい処理の結果です。このマイナス残高は、翌月以降に徴収する源泉所得税と相殺され、徐々に解消されていきます。
【会計ソフト別】残高を正しく管理するための重要ポイント
ズレを未然に防ぎ、日々の残高確認をしやすくするために、お使いの会計ソフトで少し工夫することをお勧めします。
ここで非常に重要な注意点があります。預り金がズレる最大の原因の一つが、源泉所得税と住民税など、性質の異なるものを同じ補助科目や品目タグで処理してしまうことです。これらを混在させてしまうと、源泉所得税の納付額と残高が一致しなくなるのは当然です。正しく分類することが、正確な残高管理の第一歩です。
マネーフォワード会計をご利用の場合
「預り金」の勘定科目に「補助科目」を作成するのが非常に有効です。「預り金」の中に「源泉所得税」「住民税」「社会保険料」といった補助科目を個別に設定しましょう。
これにより、それぞれの税金・社会保険料が明確に区別され、混在を防ぐことができます。総勘定元帳で「預り金/源泉所得税」の補助科目だけを見れば、納付額との照合が格段に楽になります。
freee会計をご利用の場合
freeeでは、取引の登録時に「品目」や「メモタグ」を活用すると便利です。
給与や報酬の支払い取引を登録する際に、「源泉所得税」「住民税」といった品目を明確に使い分けましょう。さらに「源泉所得税_給与分」「源泉所得税_報酬分」のようにタグで細かく分類しておけば、後から特定の源泉所得税だけを抽出して集計するのが容易になり、ズレの原因調査もスムーズに進みます。
それでも解決しない…その不安、当事務所にご相談ください
「チェックリストを見ても、やっぱりズレの原因が分からない…」
「毎月の給与計算から会計処理までの流れが複雑で、負担に感じる」
「この預り金のマイナス残高、本当に合っているのか不安…」
もし、このようなお悩みや会計処理の煩雑さに少しでも手間を感じるようでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
私たちは税務と会計のプロフェッショナルとして、貴社の会計データを丁寧に拝見し、現状の確認からズレの原因特定、適切な修正、そして今後の効率的な経理体制の構築まで、責任を持ってご支援いたします。
源泉所得税の管理は、企業の信頼に関わる重要な義務です。専門家の力を活用し、正確でスムーズな税務処理を実現しましょう。
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [コラムまとめページはこちら]