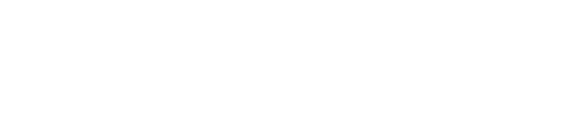COLUMN
コラム
C005|クラウド会計で帳簿を乱さないための5つの鉄則|自計化を成功させる実務ポイント
「楽になるはずが…」クラウド会計導入後に帳簿が乱れる理由
「クラウド会計を導入すれば経理が楽になると思ったのに、なぜか預金残高が合わない…」「自動で帳簿ができるはずなのに、申告に全く自信が持てない…」
freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトの普及で会計入力は確かに便利になりました。しかしその一方で、気づかないうちに帳簿が「ぐちゃぐちゃ」になってしまうご相談が、当事務所にも日々寄せられています。
この記事では、便利なはずのクラウド会計でなぜ帳簿が乱れてしまうのか、そしてそれを防ぐために絶対に守るべき「5つの鉄則」を解説します。
帳簿をクリーンに保つ!自計化で守るべき5つの鉄則
帳簿が乱れる原因のほとんどは、「自動化の過信」と「運用のルールが決まっていない」ことにあります。以下の5つの鉄則を守るだけで、帳簿の精度は劇的に向上します。
鉄則1:連携データは「事業用」に限定し、最小限に
銀行口座やクレジットカードを簡単に連携できるのがクラウド会計の魅力ですが、ここに最初の落とし穴があります。プライベート用の口座やカードまで連携させてしまうと、事業と関係のない取引データが大量に流れ込み、帳簿が混乱する最大の原因となります。
【今日からできること】
連携する口座・カードは事業専用のものだけに絞り込みましょう。もし、やむを得ずプライベートの支出が混ざってしまった場合は、後述する「事業主貸」などで正しく処理する必要があります。
鉄則2:「自動仕訳ルール」を過信せず、定期的に見直す
一度設定すれば、同じ取引を自動で仕訳してくれる学習機能は非常に便利です。しかし、最初に間違った勘定科目を設定したまま放置したり、イレギュラーな取引に気づかず自動処理されたりするケースが後を絶ちません。
特に、freeeの「無視」やマネーフォワードの「対象外」といった機能は、安易に使うと帳簿残高と実際の明細がズレる直接的な原因になるため、細心の注意が必要です。
【今日からできること】
プライベートな支出などは「対象外」にするのではなく、個人事業主なら「事業主貸」、法人なら「役員貸付金」などで、取引があった事実を残す形で正しく処理しましょう。そして、月に一度は自動仕訳ルールの一覧を見直し、おかしな設定がないか点検する習慣をつけてください。
鉄則3:OCRは”アシスタント”。最後は「人の目」で確認する
レシートをスマホで撮影するだけでAIが読み取ってくれるOCR機能は、入力の手間を減らしてくれます。しかし、その精度は100%ではありません。あくまで「下書きをしてくれるアシスタント」と捉え、最終確認は必ず人の目で行いましょう。
【今日からできること】
読み取られた「日付」「金額」「取引先名」などが正しいか、必ず元のレシートと見比べて確認してください。特に、軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在しているレシートは、AIが誤認識しやすいポイントです。
鉄則4:そもそも「手入力」を減らす仕組みを作る
手入力の機会が多ければ多いほど、入力ミスや漏れが発生する確率は高まります。経理の効率化とは、手入力の速さを競うことではなく、手入力そのものを減らす仕組みを作ることです。
【今日からできること】
事業で使う経費は、可能な限り「事業用クレジットカード」または「事業用デビットカード」で支払うように徹底しましょう。これにより、取引データが自動で連携され、手入力の手間とミスを大幅に削減できます。また、Amazonビジネスのような法人向けサービスを活用するのも有効です。
鉄則5:「証憑」なき入力は無効。整理・保管を徹底する
会計帳簿への入力は、必ずその根拠となる「証憑(しょうひょう)」、つまりレシート・領収書・請求書・通帳のコピーなどに基づいて行わなければなりません。
これらの証憑がなければ、たとえ帳簿に記載があっても、税務調査で経費として認められない可能性があります。
【今日からできること】
証憑は月別にファイリングするなど、ご自身が管理しやすい方法で、法律で定められた期間、必ず整理・保管してください。スキャナ保存(電子帳簿保存法)を検討する場合は、満たすべき法的要件が細かく定められているため、自己判断せず専門家である税理士に相談することをお勧めします。
「税理士いらず」の落とし穴|ソフトだけでは完結しない理由
「会計ソフトだけで確定申告までできる」という広告も見られますが、それには「適切な処理ができている」という大前提があります。もし帳簿の記載要件を満たしていなければ、青色申告特別控除(最大65万円)が取り消されたり、消費税の仕入税額控除が否認されたりするといった、深刻なリスクが伴います。
結果として、税理士に支払う費用をはるかに上回る追加の税負担が生じることも珍しくありません。
まとめ:「入力は自分で、最終チェックはプロに」という賢い選択
自計化は、自社の経営状況をリアルタイムで把握できる素晴らしい取り組みです。しかし、不安を抱えながら間違った帳簿を作り続けては意味がありません。
「日々の入力は自分で効率的に行い、月に一度、あるいは決算前に、専門家である税理士に健康診断のようにチェックしてもらう」という形が、最も費用対効果が高く、安心できる方法だと私たちは考えています。
当事務所では、クラウド会計を使った自計化支援も積極的に行っております。「できるところまでは自分でやりたいけど、不安がある」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
他のコラムもあわせてご覧ください
当事務所では「会社設立」「クラウド会計」「資金繰り」「会計ルール基礎」など、
経営者の皆さまに役立つテーマをシリーズ形式で整理しています。
今回の記事以外にも関連するコラムをまとめていますので、ぜひご覧ください。
➡ [コラムまとめページはこちら]